
こっちでは冬休みに入った。休みは一ヶ月程度で、日本より少し短いような感じだ。休みが終わるのが嫌いなので、それならいっそ休みなんてなくていいと休みの終わりが近づくと思う。 そんなことはさておき、ある本を読んでいて、すごいと思うことがあった。この本の内容の話をして、それがいいか悪いというような物を始めてしまうと、それは彼のなんらかの種の偏りを通して、日本を見ることになってしまうため、内容については評価しないでおこうと思う。だから、この文章では内容ではなく、彼がこの本を書くために用いたであろう技術について焦点を当てる。(しかし、その技術ももしかしたら、彼という偏り、言い換えれば、彼の特徴や彼だからできるというようなことに多分に影響されているかもしれない。) その本は「日本その日その日」というエドワード・S・モースという学者である。もしかしたらこの名前を聞いたことがあるかもしれないが、それは彼が日本で大森貝塚という貝塚を発見したことで有名だからである。彼のこの偉業は一旦横に置いて、この本は彼の日本での日記のような形式になっている。日本に着いた日から書かれ始めている。彼はまだ日本に上陸する前から、船で日本人に岸へ運んでもらっている最中から日本人という彼にとって新しいものに胸を躍らせている。西洋国家の法支配の国では考えられないような世界がそこには広がっていたんだということに関する驚きが文を通じてひしひしと伝わってくる。 彼の日記はまるでSF小説の中の架空の街についての話に思える。なぜなのか、それはおそらく、当時の日本が私にとっても馴染みのないものであることと、彼の言語による描写能力の高さに起因しているのだろう。当然その時の日本を経験したことなどないのに、彼の文を読んでいると、過去の一時代の中にタイムスリップしたような感覚になる。文章から、仮想空間が生成されるといった感じだ。きっと彼は世界を描写する時に世界を描写するということに関して、すごく真面目なのだろう。だから、私だったら、意識にすら入らずに見落としてしまうことについても、見落とさずにしっかりと描写することができるのだと思う。また、この日記の文はとても知識量が多い。彼が学者であるということもあり、調査力がすごいのだろうか。世界をよく見ているのだろう。私もこの報告書を彼の日記のように書きたいと思った。果たしてできるだろうか。観察するだけで、疲れて頭が痛くなりそうな予感がする。 この本が私にとって近いものであるように感じた一つの理由はちょうど私も異国の地にいて、それまでの慣れ親しんだ常識とは違う世界にいるという状況の近さであろう。 彼は単に語彙を多く持っているという訳ではない。文章を読んでいる人にその文から映像を想像させるのが上手いのだ。確かに語彙をたくさん持っているというのはあるだろう。しかし、それだけではない。物をよく見ているし、文から映像を想像する際にどのような情報が必要かを理解し、それを的確に文章の中に入れているのだ。だからより正確には語彙の使い方が上手いという言い方の方がいいかもしれない。
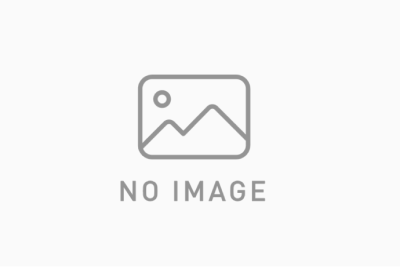
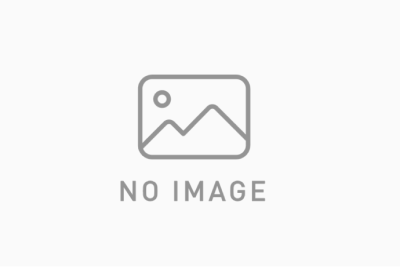
| 内訳 | 費用(現地通貨) | 日本円換算 |
|---|---|---|
| 家賃 | 1,047 | 30,700円 |
| 水道光熱費 | 0 | 0円 |
| 学費・教材費 | 0 | 0円 |
| 交通費 | 200 | 5,864円 |
| 通信費 | 0 | 0円 |
| 食費・その他 | 3,000 | 87,966円 |
| 合計 | 4,247 | 124,530円 |