
今月はクリチバに旅行した。その際に先住民族の生活や歴史に関する博物館に訪れた。そこには当時使われていた生活用品や何かの儀式のために用いられたであろう装飾品や道具が並んでいた。また、先住民族の人たちの瞬間を切り取った写真なども展示してあった。その中に木で編まれたカゴのようなものも展示されていた。しかし、ただ木で編まれただけではなく、その中には粘土か何かでコーティング加工のようなものがされてあった。これは発見された後にそのカゴを維持するために施されたものかもしれないが、もし、それが作られた当時からその加工がされていたのならと考えた時に石器や土器に対するある考えが浮かんだ。私は以前まで、縄文土器などについている模様は模様をつける目的で土器を作る過程においてヒモなどを巻き、意図的につけたものだと勝手に思っていた。しかし、このコーティングされたカゴを見た時、実はこの認識は間違っていたのかもしれないと思った。つまり、縄文土器などについている模様は模様をつけようと思ってつけたのではなく、土器を作る過程で必然的についてしまったものなのではないかということである。どういうことかというと、まず、ヒモで編まれた土器の雛形を作る。そしてそこに粘土をつけて土器の形にするのだ。こうすることで出来上がった時にはその土器に紐の模様が付くのだ。この方法で作れば、雛形がない状態で作るより簡単に作れるのではないかと思われる。粘土の塊を器の形に形成するよりも、雛形を作ってそこに粘土をくっつけていく方が容易ではないだろうか。また、作り方によっては同じような形や大きさの容器をいくつも作れるかもしれない。 これを機に土器について調べてみたところ、どうやら最古の土器は無文土器で模様が全くない土器であったそうだ。また、縄文の模様は撚り紐を転がしてつけられたと考えられているようだ。私も高校までで学んだ時の考えではこれと同じように意図的に、そして容器を作った後で模様をつけていたのだと思った。でももしかしたら、模様は意図的なものではなく、制作過程で必然的に、そして無意識的についてしまったものなのではないかと考えることも可能ではないだろうか。
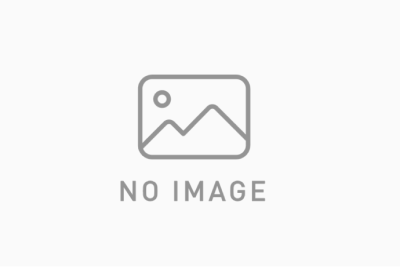
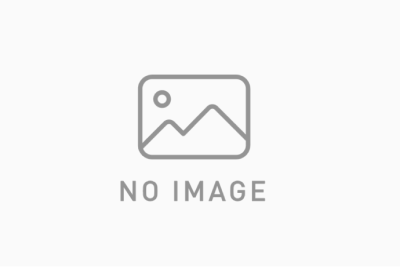
| 内訳 | 費用(現地通貨) | 日本円換算 |
|---|---|---|
| 家賃 | 1,069 | 31,723円 |
| 水道光熱費 | 0 | 0円 |
| 学費・教材費 | 0 | 0円 |
| 交通費 | 230 | 6,825円 |
| 通信費 | 0 | 0円 |
| 食費・その他 | 3,552 | 105,407円 |
| 合計 | 4,851 | 143,955円 |