月次報告書 2018-06
プロフィール

生活編
おわりとはじまり。
私のダートマス大学での留学生活は現地時刻で2018年6月6日付けで終わりを迎えました。 まず、個人名は伏せさせていただきますがこの場をお借りて交換留学を通してお世話になった方々に感謝申し上げさせていただきます。留学生活の中でダートマス大学の先生方、仲間達、関係者の方々には常に背中を押されました。そのような現地でのサポートなしに数々の困難を乗り越えることは不可能であったと思います。又、神田外語大学の先生方、仲間達、国際交流科の方々には留学の準備期間からこれまでにかけて長期的に支援していただき、日々の励みとなりました。最後に、常に私を信じ、側で支えてくれた両親に感謝申し上げます。ありがとう。 私のダートマス大学での学びはこれを持ちまして終了となりますが、私の学び自体はまだ終わりではありません。ダートマス大学では非常に多くのことを吸収し、成長することができました。しかし、ダートマス大学での10ヶ月間で学んだことは私が生涯を通して学ぶことのごく一部でしかありません。これからまた新たな生活がはじまります。無知を自覚して学びに対してもっと貪欲になり、自分の人生を豊かにしていくと共に将来的には何らかの形で社会に貢献していきたいです。 最後に繰り返しにはなりますが、応援ありがとうございました。これからも引き続き精進していくのでよろしくお願い致します。
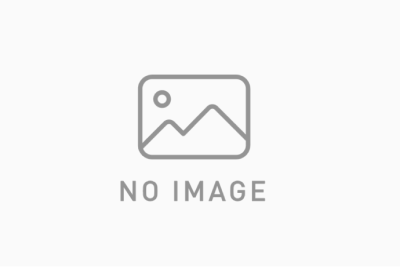
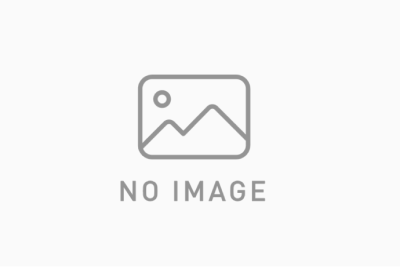
住居形態
学生寮
無線LAN(Wi-Fi)
月額費用
アメリカ ドル
102.07円
| 内訳 | 費用(現地通貨) | 日本円換算 |
|---|---|---|
| 家賃 | 700 | 71,449円 |
| 水道光熱費 | 0 | 0円 |
| 学費・教材費 | 50 | 5,104円 |
| 交通費 | 800 | 81,656円 |
| 通信費 | 0 | 0円 |
| 食費・その他 | 500 | 51,035円 |
| 合計 | 2,050 | 209,244円 |
授業編
Learning
学習心理学
講義(英語)
120分
今月はテストのみでした。テストの形式は選択式問題が45問、正誤問題が5問、短いエッセイ式の記述問題が1問でした。記述問題は事前にサンプルの問題を7つ教えてもらえて、その中から1題そのまま出題されると聞いていたので事前に準備することができました。各問題につき400-500語ほどの模範解答を用意したのですが、7題分考えるのは大変でした。しかし、しっかり準備した甲斐もありテストはよくできたと思います。この授業全体を通して多くのことを学ぶことができたと感じています。担当の教授とも個人的に仲良くなることができ、これからの知識のアップデートのために読むべき本も教えていただいたので関連分野をまだまだ深く学んでいきたいです。
Cognition
認知心理学
講義(英語)
120分
今月はテストのみでした。形式は選択式で、前回のテスト後から今までの範囲から40問、最初から前回のテストまでの範囲から30問の合計70問でした。テストでは時間をたっぷり使えたので自分の実力を出し切ることができました。この授業では人間の学習、記憶、意思決定、物体認知などの認知能力を概観したのですが、私は特に「コネクショニズム」という理論に強く興味を持ちました。コネクショニズムの目標は脳の仕組みを参考にしたネットワークモデルを使用して人間の認知の仕組みを解き明かすことです。この授業ではコネクショニズムに関して深いところまでは学ばなかったので、これから自分で文献を読み込んだり、実際に自分で人間認知のネットワークモデルをプログラミングで作ってみたりしたいです。
Discourse, Culture, and Identity in Asia and the Middle East
アジア・中東の言語人類学
講義(英語)
0分
今月は授業はなく、リサーチペーパーの提出のみでした。リサーチペーパーのテーマは授業で学んだことを基にして教授と相談しながら自分で決めることができます。私は文献を通したリサーチを行い、先行研究を基に日本語の文章構造の特徴、英語との比較、文化的背景、文章のジャンルや目的による構造の違い等を自分なりの考察と共に4000語ほどにまとめました。この授業では、文化によって異なる言語行動(verbal behavior)について主に学びました。例えば、日本と西洋の沈黙の意味や相槌の意味の違いです。こうしたことを学ぶことを通して、言語行動は単に「英語を話す」、「日本語を話す」こと以上に複雑だと知ることができました。この文化に特有な言語行動の複雑性の理解は言語教育にも生かすことができると思います。例えば、近年の日本の英語教育では会話能力が重視されるようになってきました。しかし、英語を話せることと他国の人との円滑なコミュニケーションは本当にイコールで結びつくのでしょうか?英会話能力に問題がなくても日本人が習慣的についしてしまうお辞儀、謙遜、過剰な相槌などが国際的なコミュニケーションが行われる場においてどういった影響を持つと思いますか?この授業はこのような問題について考えていくために必要な知識の基盤を形成するには非常に示唆に富むものであったと感じています。