月次報告書 2018-09
プロフィール
生活編
寮生活
台湾にきて一ヶ月が経ちました。今月の生活編で寮生活についてです。 留学先の開南大学では滞在先に寮かアパートか選択できます。私は前者の寮を選びました。寮は部屋は一部屋に私も含めて四名います。ルームメイトは全員台湾の学生で、一年生です。うち二人は日本語学科なのと、もう一人は日本のアニメが大好きなので私が日本人ということもあり、みんな親しくしてくれます。しかし全員日本語も英語も簡単なものしか通じないのでグーグル翻訳を片手に中国語でコミュニケーションをします。そして台湾にきて驚いたことがあるのですが台湾人は実家が大好きなので週末になるとみんな家に帰ります。もちろん大学から実家が遠い人は一、二ヶ月に一回ですが私のルームメイトはみんな実家から大学まで近いので、金曜日の午後になって寮に戻ると誰もいないです。せっかくの土日なのにルームメイトだけでなく、台湾人の友達もみんな実家に帰ってしますので少し寂しい気がします。
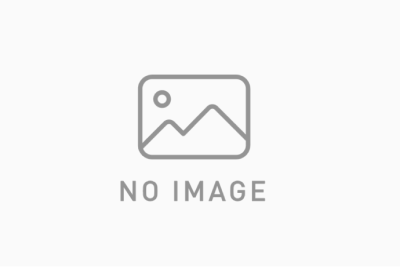
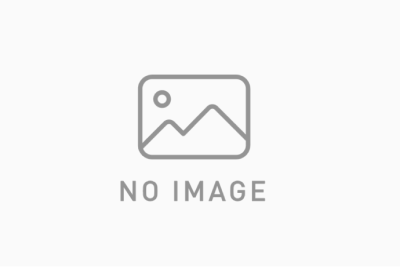
住居形態
学生寮
無線LAN(Wi-Fi)
月額費用
台湾 台湾ドル
3.7円
| 内訳 | 費用(現地通貨) | 日本円換算 |
|---|---|---|
| 家賃 | 3,300 | 12,210円 |
| 水道光熱費 | 200 | 740円 |
| 学費・教材費 | 100 | 370円 |
| 交通費 | 550 | 2,035円 |
| 通信費 | 799 | 2,956円 |
| 食費・その他 | 20,000 | 74,000円 |
| 合計 | 24,949 | 92,311円 |
授業編
中級華語(上)
IHP中級中国語(上)
語学(地域言語)
360分
出席回数は3回です。
中国語の基本的な会話を学習しました。
今月は身の回りの物やその数え方についての中国語を覚えました。
科學思維的發展與應用-Development and Applications of Thought Sciences-
科学思想の発展応用
講義(英語)
360分
出席回数は3回です。
この授業では『An Introduction to Science and Technology Studies』という教科書を用いて先生が科学史について解説します。
今月は第1章と第2章を中心に学習しました。
第1章では第2章のThe Kuhnian Revolution以前までの科学技術の歴史を哲学からの視点に基づいて学習しました。この章では反証可能性によって科学と非科学は区別されることについて学びました。例えば「全ての人間は必ず最後は死ぬ」ということを実証するためには亡くなった人の情報を何百億と集めて実証するのではなく「不死身の人がいる」という反証事例の存在を証明することによって実証すべきであるということです。
第2章はThomas Kunhという科学哲学者が起こしたThe Kuhnian Revolutionについてです。Thomas Kunhは科学技術の進歩(歴史)はパラダイムシフトによる段階的な過程として捉えなおすことができることを提唱し、大きな論争を起こしました。この章ではThe Kuhnian Revolutionとは何かについて学びました。
Risk Management
危機管理
講義(英語)
540分
出席回数は3回です。
今月は金融におけるリスクとはどのようなものがあるのかについて学びました。
金融市場におけるリスクは主にMarket Risks(市場リスク)Liquidty Risks(流動性リスク)Credit Risks(信用リスク) Operation Risks(業務リスク)の4つがあり、それぞれのリスクの特徴とその対象法について学習しました。
会計学 -Accounting I-
会計学 I
講義(英語)
540分
出席回数は3回です。
今月は会計の基本的な仕組みについて学習しました(例えば資産=負債+資本[資本金+留保利益{収益ー費用ー配当金}])
基本的に中間テストまでは日本でいう簿記三級と同レベルの内容なので、すでに日本で簿記三級を学習済みの私にとってはさほど難しい内容ではないですがこの授業ではIFRS(国際会計基準)について学習するので簿記よりもさらに大きな枠組みと仕組み(抽象的で概念のようなもの)を英語で学ぶので多少その概念を英語で覚えることには苦労します。またこの授業で学ぶ会計学(IFRS基準)はイギリスを中心とした新しい基準で日本の会計基準とは異なる点があるので、今まで日本で学んだこととは違うため理解に苦しみます。
例えば日本やそのほか多くの国では原価主義会計という制度ですが、このIFRS(国際会計基準)では時価主義会計を軸にしています。原価主義会計とは取得したコストの原価を財務諸表に記載することで、時価主義会計は特定の資産または負債について毎期末の時価をもとに評価します。この制度の違いにより仕分けや財務諸表の計算の違いがあるので日本の基準と別にこの方法を英語で覚えないといけません。
統計学 -Statistics
統計学
講義(英語)
540分
出席回数は3回です。
今学期は後期にR言語を用いてコンピュータで統計分析をするため、それに向けての統計の基礎を学びます。
この授業の目的はビジネスで使える統計の技術習得を目標にしています。
今月学習した統計学の内容:Nominal, Ordinal, Ration, Internal, Frequency Distribution
歴史名著講読 -History
歴史名著講読
講義(英語)
360分
出席回数は3回です。
今月は戦略と戦術の違いにつてい学習しました。戦略と戦術は一見すると似ているようですが意味は大きく違います。
戦略とは中長期的な計画でありどのように戦いに勝つかを考えることです。一方、戦術は短期的な計画でどのように戦うのか細かいところまでを考えることです。たとえどんなに戦術が優れたとしても、中長期的な視点で見る戦略が無ければ戦いに勝つことはできませんし、どんなに優れた戦略があっても戦術が無ければ具体性にかける妄想で終わってしまします。
また、孫子の兵法を基に現代のビジネスにどのように活かせるのかについても議論しました。
台湾経済発展論 -Economic Development R.O.C.(Taiwan)
台湾経済発展論
講義(英語)
540分
出席回数は3回です。
台湾の地理や近現代の経済史について学習しました。
