
2月に入り、留学生活もいよいよ終盤に差し掛かってきました。 勉強に遊びにと約6か月と少しを振り返るとかなり充実した生活が出来たという思いと もう少し時間を上手く使えばさらによき学びが増えたのではないかなとも実感しています。 2月はテストやエッセイの提出、そして中間の休み2/21~3/1がありました。 <授業>やはり授業で一番大変なのは宗教の授業です。私のいるコンコーディア大学はキリスト教の大学で他の大学と比べてもかなり宗教色が強く、キリスト教に関する行事がいくつもあり、宗教学も必須科目としておかれています。なので、日常から宗教について考える機会が多く、自分の価値観や考えの根本にあるものを考える時間が自然と多くなりました。現在、コンコーディア大学には神田からの学生が3人いますが、どの学生も宗教に関する行事に積極的に参加して学びの機会を得ています。話を授業に戻すと、授業でも留学生以外の学生はおそらく全員がキリスト教なので、その分野に関しての知識は基本頭に入っています。なので、どうしても課題をこなすスピードやエッセイの質に違いが出てしまい私は単位を取るのに必死です。ただでさえコンコーディアの授業は少人数制で一つ一つの授業の内容が濃く、予習に時間がかかるので授業を取る際はよく考えて選択することが重要です。 <生活>普段の生活は季節が変わったからと言っても特に変わることはありません。そもそも大学が街にあるわけではないので、行ける場所も限られています。バスを使うことで、行動範囲は広がりましたが、それでも買い物に行く場所はウォルマート、ターゲットか隣町にある大きなショッピングモールがほとんどです。あとは、友達に車でバスで行けないところへ連れて行ってもらいます。食事も基本は大学内の学食、週末は外食へ行きます。 <中間休み>後期に入ってから1回目の短期の休みでした。私は専門学校時代の友達が日本からアメリカに来てくれるということでニューヨークとワシントンDCに行って来ました。初日からシカゴ→NY間の飛行機が欠航になりシカゴの空港で一夜を過ごすという波乱の幕開けでしたが、NYの人種の多様性と政治、商業の中心地に行けたことはとてもいい経験になりました。9/11の跡地であるGround zeroや国連本部、ホロコーストミュージアム、そしてアメリカの歴史博物館で日本では目にしたり聞くことのできないことを学ぶことができたのも大きな収穫です。 留学生活も残りわずか。悔いのないように最後まで楽しむことを忘れずいろいろ学んで帰りたいと思います。
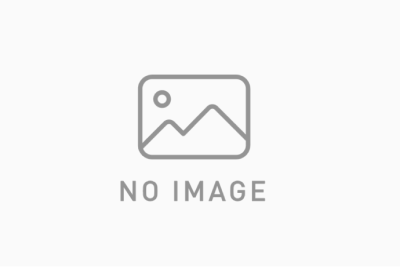
| 内訳 | 費用(現地通貨) | 日本円換算 |
|---|---|---|
| 家賃 | 387 | 39,501円 |
| 水道光熱費 | 0 | 0円 |
| 学費・教材費 | 0 | 0円 |
| 交通費 | 580 | 59,201円 |
| 通信費 | 30 | 3,062円 |
| 食費・その他 | 1,093.72 | 111,636円 |
| 合計 | 2,090.72 | 213,400円 |
