月次報告書 2018-02
プロフィール

学科
国際コミュニケーション学科
学年
3年
専攻
国際コミュニケーション専攻
留学期間
2017-08-01 ~ 2018-05-31
留学種別
推薦
生活編
まだまだ冬のミネソタ
2月に入り、身を刺すような寒さは和らいできましたが相変わらず雪は結構積もっています。授業が忙しく、課題も毎週沢山出されるため、不覚にも来月の春休みが待ち遠しいです。今月上旬にはDragon Frost Week という週があり、キャンパス内でアイスクリームやマカロニチーズを配るイベントがあったため友達と一緒に行ってきました。また前のセメスターから引き続き加入しているLearning Communityのイベントでは終末にスキーや映画を観に行ったりし、忙しい授業の合間を縫ってかなり充実した時間を楽しむことができました。他にも休日には友達と買い物へ行ったり、同じ神田からの留学生友達の誕生日パーティーを開いたりしました。 平昌オリンピックが始まり、アメリカでもテレビや新聞で連日オリンピック選手たちの活躍が取り上げらています。また個人的には神田の学生で通訳ボランティアとして海外で活躍している人もおりとても良い刺激になりました。彼らを尊敬する気持ちと負けてはいられないという気持ちの両方が感じられた1ヶ月となりました。
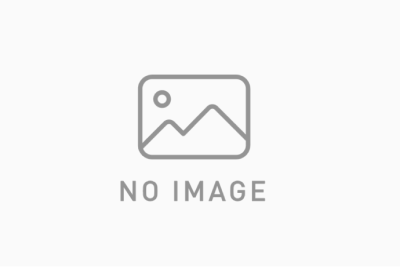
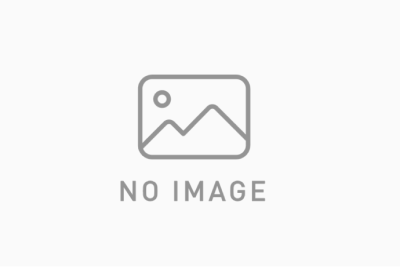
住居形態
学生寮
無線LAN(Wi-Fi)
月額費用
アメリカ ドル
102.07円
| 内訳 | 費用(現地通貨) | 日本円換算 |
|---|---|---|
| 家賃 | 1 | 102円 |
| 水道光熱費 | 0 | 0円 |
| 学費・教材費 | 0 | 0円 |
| 交通費 | 0 | 0円 |
| 通信費 | 45 | 4,593円 |
| 食費・その他 | 100 | 10,207円 |
| 合計 | 146 | 14,902円 |
授業編
Social Problems
社会問題(50分×週3回×4週=600)
講義(英語)
600分
今月は地球温暖化、Neo Colonialism(帝国主義時代の名残の先進国と発展途上国の格差)、郊外と都心の居住地と格差について学びました。特に帝国主義の影響が未だに続いていることは興味深く、またそのような国の中ではIMF(国際通貨基金)の借金を返済できない国も多い問題と、戦後のアメリカでGI Billを受けることのできた白人は郊外に家を建てることができ、給付を拒否された黒人が都心に取り残され現在も格差がある問題に対して自分の考えを話す授業は、様々な学生の異なる立場からの意見を聞くことができ、とても勉強になりました。都会に住む人の特徴(低所得層、経済的や高齢等の問題で移住出来なかった人々、海外から移り住んだ人、学生や新社会人などの独身層、芸術家層)はアメリカの都市と東京で違いはありませんでした。改めて授業で習うことで言われてみればそうだなと感じることが沢山あり、またどれも問題解決が容易ではないもので、日々の生活の中では全く感じないけれども実は深刻な問題が身近に存在していることに気づくことができました。
General Psychology
心理学(75分×週2回×4週=600分)
講義(英語)
600分
今月は性別とジェンダー、感覚と知覚、学習、そして記憶について週ごとに学びました。特に学ぶことが多かったのは性別とジェンダーについての週です。アメリカの大学ではLGBTの団体が多く存在していて、ここMSUMにもありますが、その方達によるプレゼンテーションも授業であり、今までの常識を覆されるようなことを学ぶことができたと感じています。その他、感覚と知覚や学習の項目では神田で受けていた教育心理学の授業で習ったこととほぼ同じ内容が出てきたため、より理解しやすかったです。
Strategy and Tactics in Public Relation
PR戦略
講義(英語)
600分
ケーススタディのディスカッションが続いています。毎週3つから4つのケースについて話し合います。今月話しあったもので印象に残っているものはMcDonald'sの子供が遊ぶエリアの衛生環境が劣悪だった件、養鶏場で鶏を不適切に扱っていた件、ソニーの顧客情報が流出した件などですが、一つ一つの事例の後企業がどう対応したかが興味深く教科書を読んでいても楽しいものばかりです。グループのメンバーが話している中に入って行くことは大変ですが、話をよく聴きながら自分の意見を述べるタイミングがだんだんと掴めるようになってきて積極性が増してきたと思います。まだ自分の考えをスラスラと述べることは難しいですが相手に自分の意見を上手く伝えることに重点を置きなが流暢さも磨けたら良いと思います。
History of the United States Since 1877
アメリカの歴史 1877年より
講義(英語)
600分
今月の上旬は第一次世界大戦の頃のアメリカを中心に学びました。14日には中間テストがあり、今までに習った内容を総復習してテストに臨みました。その他"Black No More(黒人はもういらない)" のリーディング課題が課されており中間テストの翌々週に確認テストで問題が出されましたが、読み始めたのが遅かったため、結局最後まで読むことができず出来あまり出来は良くなかったです。まだもう一つリーディングの課題があるため次回は早めに準備を進めておきたいと思います。
今月の後半はフランクリン・ルーズベルト大統領と第二次世界大戦の頃について授業で習いました。中学や高校で習ったアメリカ史と違い、アメリカ側から見た細かい部分を学べる為非常に興味深く学んでいてとても楽しいです。
Crisis Communications
クライシスコミュニケーション
講義(英語)
600分
今月はビジネスクライシスのレポート提出と模擬記者会見がありました。レポートではユナイテッド航空の乗客がオーバーブッキングのために強制的に座席から引きずり降ろされた件について調べレポートにまとめました。また模擬記者会見では4人のグループに分かれて本物さながらの模擬記者会見を行いstakeholders(利害関係者)からの質問に協力して答えました。授業ではクライシスがどのようにメディアで報じられ、利害関係者がどのような情報を必要とするかなどを学びました。
今月はチャプタークイズがオンラインで出され、出題された質問にレポートで取り上げたトピックについて答えるものでした。レポートからの抜粋でもよいとのことで、負担が軽くかなり助かりました。
Mass Media Ethics and Issues
マスメディアの倫理と問題
講義(英語)
600分
今月の授業では各国の放送倫理について学び、テレビに出演する人の人権が軽視されないようなルールが定められていることを学びました。つい最近では日本の年末の特番で黒塗りの演出が人種差別に当たるのではと言ったような議論がありました。国によってもどのような系統の演出が好まれるかが違い一概にルールを同じにすることはできませんが、番組を制作する際にはどこの国の人が見ても不快感を感じないような演出になるよう出来るだけ配慮はすべきだと感じました。